

そんなお店の事情を知っておくと、こちらも対処しやすいかも…。
そんな業界の裏事情を知っておくと、普段の生活もちょっとだけお得になることもありますよ。
でも、お店の人も大変ですよね…
忘れ物を見つけても連絡しない一流ホテル

たとえば、A氏という人物が、前日宿泊したホテルにセーターを忘れてきたとする。帰宅後、A氏が荷物を広げたところ、セーター行方不明の事態に気づく。(しまった!)と、その日一日を振り返ってみるものの、記憶はおぼろげ。ホテルの部屋に置き忘れてきたような気もするし、チェックアウト時は肩にセーターを巻きつけていたような気もするし……。そんなとき(○○ホテルは一流だし、忘れ物があれば親切に連絡してきてくれるだろう。とりあえず待ってみるか)などと、のんびりかまえているようでは、セーターはずっと行方不明のまま。ではどうすればいい?何はさておきホテルに連絡。ホテルに忘れた可能性が少しでもあるようなら、それが正解だ。待っていたところで、向こうからの連絡はたぶん来ないからである。なぜなら、一流と言われるホテルほど、普通『お客様の忘れ物をお預かりはするが、原則的に連絡はしない』という忘れ物対策マニュアルがあるからだ。ホテルともあろうところがそんな気遣いもしてくれないなんて!などと怒るのは早い。もちろんそこには深いワケがあった。早い話が、お客もいろいろ、宿泊の目的や事情もいろいろ、ということは100人のお客がいれば、100とおりの宿泊のパターンがある。たとえば、ありかちなのがオヤジの愛人同伴お忍び旅行というパターン。そんなお客の忘れ物を知らせるために、オヤジの家族に連絡をとってしまったら?その1本の電話からすったもんだになる可能性は大。「私にナイショで若い女となんか!」と逆上する妻。シドロモドロで言葉も返せない夫。こうなると小さな親切もただの迷惑でしかなくなる。ホテル側はそのお客に恨まれ、二度と利用してもらえなくなるかもしれない。ほかにも、親にはナイショの若者カップル客、会社にも妻にもナイショのおさぼり旅行客など、宿泊を知られたくない諸事情をかかえたお客はけっこういるものだ。。それにワケありでなくても、使用済みの下着の忘れ物などは、たぶん連絡したところで迷惑がられるだけだろう。要は、必要な忘れ物ならお客側から速やかに連絡をとればいいのだ。もしホテルにあれば、必ず丁寧に保管しておいてくれることは間違いない。これも一流ならではの気遣いと言えよう。

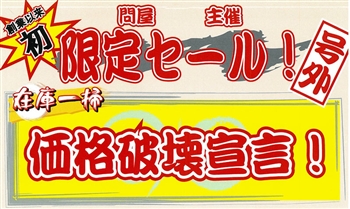

「上中下」と言わずに「上中並」と言うあたりは、日本人の知恵というもので、もしとなっていたら、そんなものを頼む人はあまりいないだろう。
それよりもさらに、曖昧なのが「松竹梅」である。人によっては、松より梅の本のほうが好きな場合もあるだろうし、よく考えれば、なぜ「松」がいちばんよくて、「竹」がその次なのかわからない。
外国人のお客さんを接待するときなど、これはどういう意味かと問われて、まともに答えられる人はいないだろう。「日本の不思議」のひとつである。
それはともかく、昼休みとか、混雑しているときにそういう店に行ったら、ほかの客が何を注文しているか、耳をすませてみよう。ほとんどが、「竹(中)」を頼むはずだ。そして、いちばん少ないのが、「梅(並)」である。
うな重の場合、「松竹梅」の差は、うなぎの大きさの違いだけということが多いから、「ダイエット中」との理由で「梅(並)」を頼むこともできるが、寿司や天ぷらの値段の差は、ネタの違いによるところが大きい。
だから、経済的理由で「梅」なんだ、と店の人やまわりの人に思われるのではないかとの心理で、「梅」は避けられるのだそうだ。
一方、「松」を頼む人は、たいがい接待か何かで、一緒の人をごちそうしなければならないとき。ごちそうするのに「竹」では気を悪くするだろうし、軽くみられたら困るとの思いで、見栄を張って「松」を頼むのである。
多くの人は、経済的理由で「梅」しか頼めないと思われるのはイヤだし、かといって、「松」では本当に経済的に無理かありそう、というわけで「竹」となる。
お店のほうも、そんなことは百も承知。「竹」のためのネタを多く仕入れている。それに、値段の設定も、ほとんどの人が「竹」を頼むという前提でしているから、実を言うと、「竹」を頼む人が多ければ多いほどお店は儲かるのだ。
「松」のネタは仕入れ値も当然高い。それに見合った利幅をとろうとすると、しなければならないが、それだと売れない。だから、「松」は値段は高いが、はそれほどではない。「梅」にいたってはもともとサービス品のつもり。
かなり高くお店の儲けつまり、経済的に余裕があるなら「松」を頼めばいいし、余裕のないときは見栄を張らずに「梅」を頼む、というのがトクする方法なのだ。





